|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
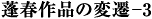 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
《山湖》から始まる実験的な風景画と、《夏の印象》などの構成的な静物画の近代的な形態と色彩による一連の作品は《望郷》が区切りとなった。その後の昭和30年代前半の一時期、蓬春は冷徹なリアリズムをめざす静物画を中心とした制作をおこなった。
「すべて写実が基盤になる、即ち写実主義(リアリズム)の基盤に立つのである。」と蓬春は述べている。自然観照から発想せよという蓬春の日常に向ける透徹した眼を感じさせ、なおかつそれが日本画として充分に消化されている。広がりをもたらす光の存在と、隈取りのように表現されている陰影が特徴であり、西欧的な静物画への傾斜を読みとることができる。
蓬春は画塾のような形態をとらなかったが、大山忠作、加藤東一、加倉井和夫、浦田正夫らが師事しており、こうした戦後の日本画壇を改革した若い原動力となった一采社の作家たちに大きな影響を与えたことも特筆される。同時代的感覚の導入と西欧近代絵画の吸収など、蓬春は戦後の次世代の画家に日本画のひとつの指針を示した。
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
《枇杷》 昭和31(1956)年 |
|
|
|
|
|
|
《冬菜》 昭和30(1955)年 |
|
|
|
|
|
|
《まり藻と花》 昭和30(1955)年 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
《籠中春花》 昭和31(1956)年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
《鰊とピーマン》 昭和30(1955)年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
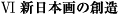 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
西洋画、古典大和絵から出発し、時代に即した日本画の創造を目指した蓬春。その画業においての最終的な課題は、和洋の真の融和であったといえる。
かつては大和絵の文学的抒情性から抜け出すために、人物や動物は画面から消し去られていた。蓬春は『新日本画の技法』の中で「構図の為に殊更に鳥を配置するようなことはせず、たとえ鳥が無くても、自然感の出るものは、強いて鳥を配する必要はない」「従来の花鳥画には、無理に不自然な鳥を配するような悪習慣がある」と述べている。
それが晩年に至り、《春》《夏》《秋》《冬》の連作を描き始めてから再び登場する小鳥の姿には、伝統的日本画の画題にあえて挑戦する蓬春の円熟した境地が窺えるようである。
現代の視点によって再び捕らえ直された花鳥画。同じモチーフにより繰り返し描かれた静物画。テーマを絞り込んだ晩年の作品では、岩絵具の清澄な色彩はますます深みを増し、洗練された構図と共に、近代的な明るさに満ちている。それこそ画家が独自に到達した新日本画の姿と見ることができるだろう。
「誰かが蓬春のレベルを維持しなくてはならない」
蓬春死後、美術評論家河北倫明氏はそう語った。蓬春芸術は、西洋画、日本画を超えた近代日本美術の一つの頂点ともいえるのである。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
《月明》 昭和35(1960)年 |
|
|
|
|
|
|
|
《宴》 昭和35(1960)年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
《陽に展く》 昭和43(1968)年 |
|
|
|
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
《春》 昭和37(1962)年 |
《夏》 昭和40(1965)年 |
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
《楓》(皇居新宮殿杉戸絵4分の1下絵)
昭和42(1967)年 |
|
|
|
|
《秋》 昭和36(1961)年 |
《冬》 昭和38(1963)年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|